TOPICS
本インタビュー企画では、bridgeメンバーが持つ専門性やルーツを深ぼりするとともに、現在進行中のプロジェクトや未来のビジョンについて紹介します。今回は、米国・日本で教育事業で起業し、その後bridgeの創業期に取締役/ビジネスデザイナーとして活動、2023年からは東北地方での産学官連携、スタートアップ支援に力を入れ、本年より静岡県浜松市に拠点を置く東海支社をベースに、”bridge NEXT”の代表として活動を開始した鈴木郁斗です。自身の経験や強み、bridge NEXTのビジョンについて聞きました。

航空宇宙業界のエンジニアを経て2009年に米国で起業。以降、シリコンバレーに活動の主軸を置き、中高大学生のアントレプレナー教育から日本企業の社内新規事業開発支援、イノベーション人材育成、米国・欧州・東南アジアでの海外事業支援、行政主導のスタートアップ支援、産学官連携プロジェクトの企画運営など、国内外でさまざまな「挑戦する人と組織」の支援に従事。各種プロジェクト企画運営や事業開発メンター、地方におけるコミュニティ形成など、幅広い分野での実績と経験・知識を活かし、日本人のQOLの向上を目指す。
もともと航空宇宙エンジニアとして働いていました。以前から「海外で仕事をしたい」という想いがあり、2009年に留学生としてアメリカに渡りました。当時お金がなく、学生ビザでは就労ができないため、自らサービスを立ち上げ、当時流行し始めたWord Pressでホームページで発信したりしながら、様々な分野で事業を立ち上げました。そのうちのひとつ、グローバル教育事業が大きく成長し、2010年に米国の就労ビザを得てカリフォルニア州に会社を設立しました。
その後東京に日本法人を立ち上げ、シリコンバレーで得た「デザイン思考」の概念を自らの起業経験や教育の文脈に紐付けて発信、啓蒙するようになり、自社のサービスにもデザイン思考を取り入れていきました。その後、経産省が「デザイン経営」を提唱し、日本企業のデザイン思考への意識が加速、当時渋谷で開業したbridge代表大長との出会いを経て、bridgeに参画し、「ビジネスデザイナー」として活動を始めました。
社内の新規事業提案プログラムの企画運営や、イノベーションを起こすための組織変革プロジェクトの支援など、国内外で様々なプロジェクトに関わってきました。
当時は東南アジア(ベトナム、マレーシア)で現地での新商品開発やユーザーリサーチを行ったり、ESG経営に力を入れる企業と、ヨーロッパ(イギリス、オランダ)で社会課題解決を実現する新規事業を創る活動をしました。
印象に残っているのは、マレーシアでの海外プロジェクトです。とある企業で新規事業のアイデアを組み立てるにあたり、現地でのデザインリサーチ(フィールドリサーチ)を実施しました。

アイデア創発のためには、現地の習慣や生活文脈を正しく理解する必要があります。そこで現地の大学生グループに入ってもらい、助言をもらいながら一緒にリサーチ活動を進めました。
3週間ほどでしたが、現地の人と心を通わせたことで、クライアントメンバーのマインドセットが変わっていったのが印象的でした。「いかに生活者を幸せにしてあげられるか」「”負”を解決してあげられるか」といった「デザイン思考」に変化していったんです。
最終的に生活者をハッピーにするための新規時事業アイデアが出来上がり、本当に素晴らしい経験でした。
話が遡りますが、4年間をアメリカで過ごした後、2013年に帰国します。シリコンバレーと東京を行き来をしながら、日本企業に対し海外研修や視察、グローバル人材、アントレプレナー人材育成プログラムの提供を続けてきました。
2014年頃になると、お客様とさらに深く向き合い、新規事業開発の課題解決のお手伝いをするようになりました。研修のコーディネートだけではバリューが出せないという課題感があったんです。
その頃、自分自身もデザイン思考による人づくり・組織づくりに関する情報発信や啓蒙活動に力を入れるようになり、デザイン思考啓蒙者として、一部ではそれなりに認知されるようになっていました。同時期にあるきっかけでbridge代表の大長と出会いました。
「イノベーション」や「事業創造」というカテゴリで着実に経験を積み、理路整然とした知識・経験を持っている大長に惹かれました。
大長は私と同じようなところがあり、一方でそれぞれにないものを持っていて、お互いの強みを融合すれば、仕事のダイナミクスが加速するのではないか?という直感がありました。
その頃のbridgeは海外での事業展開や、起業家育成に力を入れていくタイミングで、大長が求めていたアントレプレナー教育や海外事業の経験がある人材と、私が力を入れようと考えていた新規事業開発のノウハウや、マインドセットを啓蒙していくbridgeの活動がちょうどマッチしたのだと思います。何より、言語化できないものの、大長に対して強固なシンパシーを感じ、創業期に取締役/ビジネスデザイナーとして参画しました。

様々なバックグラウンドを持つメンバーがいることですね。私のような泥臭い起業家もいれば、スケールアップを目指して活動するスタートアップの社長もいます。プロトタイピングの専門家やクリエイティブが得意な人もいます。
お客様の課題に合わせ、様々な視点から的確な支援を提供できる体制を持っているのがbridgeの強みだと思います。
何より、自ら事業を立ち上げた経験をもつメンバーがギルド型でクライアントの様々な課題解決に貢献し、常に高いレベルでクオリティを保ちながら、楽しく仕事をしています。
あとはみんな”心”があります。自ら起業してそれぞれの世界観を目指す自分起点(利己)と、クライアントや社会に対する利他的な想い、それらに、個々の専門性が加わることで、高いパフォーマンスで価値提供できるところがbridgeの強みだと考えています。
当時、スタートアップエコシステムの形成に力を入れ始めた浜松の金融機関や行政関係者、地元企業や大学と関わりながら、東海エリアの中小企業の新規事業開発支援、産学官連携のオープンイノベーションコミュニティ形成に力を入れました。
コロナ禍で対面で集まる機会を頻繁に持てなかったことは今でも心残りですが、当時の浜松市長(現静岡県知事)の鈴木康友氏自らがコメンテーターとして参画してくださったり、当時は今ほど盛んではなかったオープンイノベーションの取り組みの気運を高める一助になれたと自負しています。

東海のプロジェクトがひと段落したタイミングで、2023年に仙台に軸足を置き、東北ではスタートアップ支援に力を入れました。
イベントを開催したり、スタートアップのメンタリングや伴走支援をしてきました。
1年半という短い期間でしたが、関係人口が増え、地域によって違う人・組織・社会の文化が同じ地方でも全く違うマインドや力学で動いていることを肌身で感じ、地域に合わせた柔軟性が求められていると強く感じました。
また、高校や大学、地域コミュニティ、行政の創業塾などで事業創造やアントレプレナーシップ醸成のための講演やワークショップの提供をさせていただきました。
そこでは、いわゆる「お勉強」ではなく、受講生にポジティブな行動変容を促すことを意識し、常に心を込めて伝えるようにしていました。
地域による文化や力学の違いについて前述しましたが、「心が動いて、行動する」という人間本来の成長欲求や冒険心は世界共通で人間誰しもが持っていて、その前提なしに知識だけインプットしても意味がないんです。
中には、私との対話で涙を流してくれる受講生がいたり、私の授業を受けた高校生たちから心を込めた感想文をたくさんもらったこともありました。
どれくらいの割合で行動変容に繋げられたかは測れませんが、自分が培ってきた専門性とポジティブな情緒で、行動を起こすインパクトを与えられたと思っています。
あとは、浜松でも同じでしたが、何か行動を起こしたくて、そこで苦しんでる若手から「鈴木さん、相談したいです。飲みに連れて行ってください。」と言われるキャラが確立されてきたことは、自分自身の大きな価値だと自負しています。若手起業家の悩みの壁打ちをしていたら気づけば朝5時みたいなこともありました(笑)。そこで消費したお金や時間が今期の業績に直で跳ね返ってくるようなものではもちろんないですし、普通に考えたら経済合理性の点では破綻しているのですが、そういう泥臭いところも含めて、挑戦する人に寄り添うあり方が、長期的に見たときに私たちの活動成果として必ず身を結ぶのだと信じています。
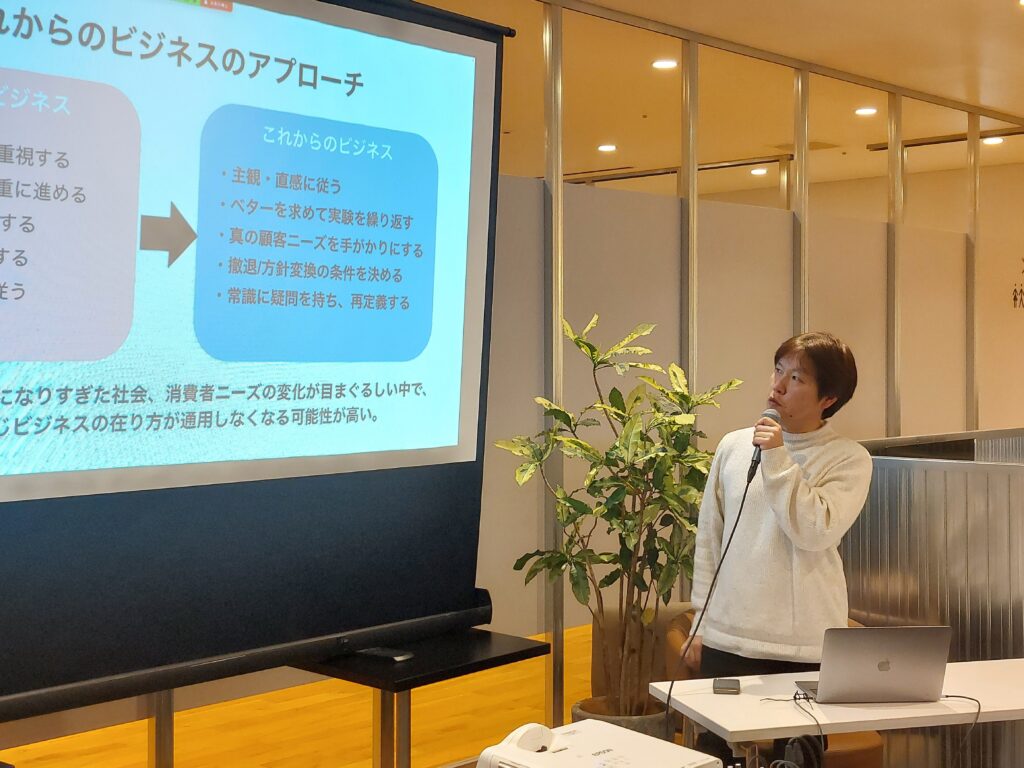
bridge NEXTでは、アントレプレナー育成、教育現場の課題解決を主軸に活動していきます。
自ら強固な志をもち、創造性を持って自分の人生・キャリアの軸を持って活動する「アントレプレナー」の育成が、今後の新たな社会を形成するうえでの喫緊の課題だと捉えています。
しかし、官民学ともに明確な指針が確立されているわけでもなく、本来これを担うべき教育従事者がその本質に向き合う余裕を持てていないことに強い課題感を感じています。
私自身、世界各国、全国各地いろんな場所で、いろんな文脈で、いろんな人と、いろんなコミュニティで、自らも起業家でありながら支援者/伴走者として関わってきましたが、私の中の結論として、「個の創造性の発掘と醸成」により、これからの社会課題を解決していく人材が増え、やがてそれが組織に波及し、社会にポジティブインパクトをもたらし、本当の意味でWell-beingな世界が実現すると信じています。bridge NEXTで物心豊かな社会の実現に寄与していく、そんな想いを込めて活動していきます。
世の中が変わっていく中で、真の意味での価値創造ができる人を増やす。
自ら新たな世界を切り開くことで、仲間を集め、創造的活動を鼓舞していける存在になる。私にとっても「NEXT」。新たなチャレンジです。
世の中のモノやサービスが高いレベルで飽和し、コモディティ化してしまっています。その中で未解決の課題に問題意識を持ち、自らの情熱や想いを起点に自ら問いを立て、新たな価値を作り出していく「アントレプレナー」の存在が、今後さらに貴重なものになるのは間違いないと思っています。
「人づくり」の領域で社会貢献していくことで、bridgeの存在価値を高めていきます。
創造性を活かして自分で新しいことを作っていくのは尊いことです。創造性を楽しめれば、人生を豊かにしていくことができます。そんな人たちを増やすことにbridgeとして寄与していきたいです。何よりも、自分自身が楽しく仕事をして、それを大きく波及させていきます。
▼bridgeのニュースレターでは最新記事、イベント情報、ケーススタディを毎月1回お知らせ致します。
メルマガの登録はこちら